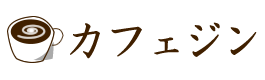ホームページのコンセプトを固める

「ウェブ商人」というホームページ制作ツールをリリースしました。wordpressをベースとしたASPサービスで、なかなかよくできたシステムと思います。(自画自賛(^^)/)
ウェブ商人の詳細はホームページに譲るとして、本ブログではリリースを記念して、ホームページ制作にあたって抑えておくべきポイントを、思いつくままに投稿していこうと思います。
といってもこの分野は非常に広いので、とりとめのない話になる可能性があるのと、やや独善的な見解になることを承知の上で、取捨選択してお読みいただければと思います<(_ _)>
さて、今日は第1回と言うことで「ホームページのコンセプト」をテーマに書いてみたいと思います。
コンセプトを固める
「コンセプトを固める」といっても「何を固めるの?」と質問がきそうです。
コンセプトを辞書で引くと「概念」がうんぬんと学説的には様々な解釈があるようです。また使われるシーンや業界によっても意味合いが微妙に違ってきます。
例えば「我社のコンセプトは」と言った場合は、経営理念に近いものになると思います。また「この小説のコンセプトは」といった場合は、作品全体を貫かれた思想のようなものでしょうか。
では「ホームページのコンセプトは?」とっいった場合の意味合いですが・
この使い方の場合は「ホームページが、何を目的として、誰に対して、どんな情報を発信するのか」について定義したものと考えられます。いってみればホームページのアイデンティティ(存在意義)を定義したものとも言えます。
コンセプトを定めるのに私のお勧めの方法は、あまり杓子定規にならず、まずは箇条書きでいいので、サイトの目的や対象者を書き出してみること。 その上で、その箇条書きをつなぎ合わせて文章化する。そうすることにより、副産物としてホームページのメインキャッチ(メッセージ)になると思います。
メインキャッチを文章化するにあたって意識して欲しいのは、そのメッセージが「顧客視点」になっているか、という点です。つまり「顧客にどうなって欲しい、どう役立つか」という点がメッセージに盛りこまれている、ということです。
例えば、ウェブ商人を例にだすと・固めたコンセプトから作ったメッセージが次ページのメインバナーに書かれています。
コンセプトにそってホームページを作る
コンセプトが決まれば、それに沿って「メッセージや、サイト構成、動線、メインとなるキーワード、デザイン、メインカラー、フォーム設計など」全てが決まってきます。
ここで、コンセプトの構成要素「目的」について少し考えてみましょう。
ホームページといっても、その運用目的は様々です。
ECサイト(通販)、リード(見込み客)獲得サイト、サポートサイト、コミュニティサイト、ニュースサイト、スタッフのヒューマンな情報発信ブログ、会社案内サイト、などなど。
当然ですが、その目的により、ホームページの作りはがらりと変わります。
ECサイトは、商品を売ることが目的になるので、どのように購入(コンバージョン)に結びつけるのか、動線設計が非常に重要になります。そこをしっかりと作らないで集客しても、穴のあいたバケツに水をそそぐようなもので、集客コストがかさむばかりです。
リード(見込み客)獲得が目的のサイトの場合は、サイトでの販売完結が難しい不動産などの高額商品や、説明を要するソリューション商品、またコンサルタントサービスなどが多い。(因みに、ウェブ商人サイトも、リード獲得が目的のサイトに分類されます。)
こういったサイトの場合、いかにホームページをじっくりと読んでもらえるかがポイントになりますので、デザインや色彩、文章構成、UPS(差別化)の明確化、といったことがポイントになってきます。
サポートサイトの場合は、安心感を与えるメッセージと色彩、双方向性、会員種別によるコンテンツの区別、場合によってはサポートスタッフの人物像など。
ここで理解しておいて欲しいのは、コンセプトによってホームページはがらりと変わるという点。サイトのコンセプトが固まれば、 後はコンセプトに沿ってホームページを作っていけばいいのです。
ホームページを自分で作るにしても、外部パートナーに依頼するにしても、まずはコンセプトをしっかり固めてから、制作に取りかかって欲しいと思います。
それでは、今日はここまで。